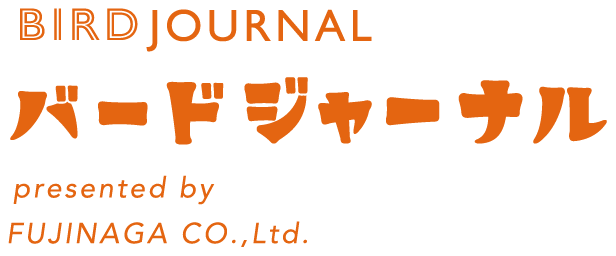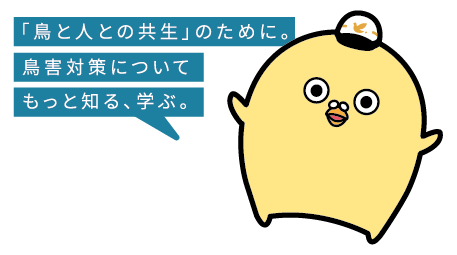「ムクドリ」と聞いて、すぐに姿を思い浮かべられる方は意外と少ないかもしれません。日本全国に生息し、私たちの生活にも密接に関わる身近な鳥ですが、その生態や特徴はあまり知られていません。
近年、ムクドリは都市化や生息環境の変化に適応し、都市部で大規模な群れを作るようになりました。その結果、夕方の駅前や繁華街では大群による騒音や糞害が社会問題となっています。一方で、その社会性や適応力の高さには驚くべきものがあります。
今回は、ムクドリの生態や被害、対策について詳しく解説します。ムクドリへの理解を深めることで、共生のヒントが見つかるかもしれません!
ムクドリってどんな生き物?
01. ムクドリの種類と特徴
ムクドリは「スズメ目ムクドリ科ムクドリ属」に分類され、中国、モンゴル、ロシア東南部、朝鮮半島、日本など東アジアに広く分布しています。
日本でよく見られる「ムクドリ」は基本的に留鳥ですが、北海道から東北地方の個体群は、冬には南へ渡ります。他のムクドリ仲間にはコムクドリ、ギンムクドリ、カラムクドリ、ホシムクドリなどがいます。

02. ムクドリの生態
私たちの身近にいる「ムクドリ」の生態について紹介します。
- 日本全国で見られる身近な野鳥
体長約24cm、体重は80~100gほど。スズメより大きく、ハトより小さい中型の鳥です。田んぼや畑などの農耕地、山裾の森林、果樹園、公園、河川敷、市街地、駅前などの繁華街にも生息しています。

- 成鳥と若鳥では色味が違う
全身は黒っぽい褐色で、目の周囲や頬に不規則な白い斑があります。黄色またはオレンジ色のくちばしと足が特徴です。オスとメスはほぼ同色ですが、若鳥は黒味が少なく、全体的にくすんだ茶色で、比較的簡単に成鳥と識別することが可能です。。

- 季節や環境に応じて食べ物を変える柔軟性
雑食性で、地上を歩きながら昆虫類・ミミズ・カタツムリなどを捕食し、春夏は果実、秋冬は木の実もよく食べます。さらには人間の残飯まで幅広く食べ、季節や環境に応じて食べ物を変える柔軟性を持っています。モモ、ナシ、ブドウ、リンゴ、カキ、ブルーベリー、サクランボなど様々な果実を食べますが、柑橘類に含まれるショ糖を消化できないため、柑橘類はほぼ食べません。

- 環境の変化により、森林から人間の生活圏に進出
もともとは森林や竹林、農耕地にねぐらを作っていましたが、都市化や環境の変化により、近年では都市部の街路樹や橋桁、電線などの人工物にもねぐらを作るようになりました。

- かつては益鳥として重宝、現在では害鳥と見なされることも
ムクドリは農作物につく害虫をよく食べていたため、農薬が発達していなかった時代には害虫駆除の役割を果たし、「益鳥」として高く評価されていました。平均的なムクドリの家族(親2羽、ヒナ6羽)が1年間に捕食する虫の数は百万匹以上にのぼるとされ、昔は害虫を1匹駆除するのに1円かかるといわれていたため、ムクドリ1家族で年間に百万円以上の利益を国家にもたらす「農林鳥」と称賛されたほどでした。
しかし、農薬の普及や環境の変化により、ムクドリは都市部に進出し、大規模な群れによるフン害や騒音被害、果樹への食害などが問題視されるようになりました。現在では「害鳥」として駆除の対象となることもあります。

- 人工物の隙間や穴への営巣が増加
繁殖期は3月~7月で、年に1~2回繁殖します。本来は樹木の空洞に営巣しますが、近年は人家の戸袋や建物の隙間など、人工物の穴を利用することが増えています。巣材には枯れ草、羽毛、獣毛、落ち葉などを用います。
卵は薄い青緑色で、1回の産卵で4〜7個の卵を産みます。抱卵は主にメスが行いますが、オスも協力する場合もあります。約12~14日で孵化し、ヒナは孵化後20日前後で巣立ちますが、しばらくは親と行動を共にしてエサの取り方の技術などを学びます。

- 高度な社会性を持ち、群れとねぐらを形成
ムクドリは高度な社会性を持つ鳥で、特に繁殖期以外は常に大規模な群れを作って行動します。数百羽から数万羽規模の大群を作ることもあります。群れを作る最大の理由は、フクロウやカラス、イタチなどの天敵から身を守るためと考えられています。エサ場の情報を共有する役割もあるとされています。
夕方になると大群になって集まり、集団で、ねぐらへ移動します。ねぐらは竹林や街路樹、電線などに形成され、天敵が近づきにくい駅前など人通りの多い場所が好まれる傾向があります。季節によって「夏ねぐら」「冬ねぐら」を使い分けることもありますが、都市化や温暖化の影響で、常緑樹や人工物を一年中ねぐらとする個体も増えています。

03. ムクドリと人の関わり
ムクドリは昔から日本人にとって身近な存在でした。そのことを示す、いくつかのエピソードがあります。
- 「ムクドリ=田舎者」!?
江戸時代、江戸の人は田舎から出稼ぎに来た人々を「椋鳥(ムクドリ)」と呼び、“やかましい田舎者の集団”として揶揄したといいます。俳人・小林一茶も、江戸で田舎者と見下され「椋鳥」と呼ばれた屈辱や疎外感を「椋鳥と人に呼ばるる寒さかな」と詠んでいます。
明治時代には、森鷗外が「日本=世界の中の田舎者」というニュアンスを込めて、海外情報を伝える連載コラムに「椋鳥通信」と名付けました。
- 土佐藩の家老がムクドリ保護のために流した“デマ”とは?
江戸時代初期、土佐藩の家老・野中兼山が「ムクドリには千羽に一羽、毒があるので食べてはいけない」というお触れを出したという伝説があります。当時、ムクドリは庶民に頻繁に食べられていたのですが、兼山はムクドリが農作物の害虫を大量に捕食する益鳥であることに気づき、保護のためにこの “デマ” を流したとされています。実際にはムクドリに毒はありません。農薬がほとんどなかった時代、この政策は非常に合理的だったと評価されています。
ムクドリによる被害とは?
ムクドリは群れで行動するため、被害が大規模かつ深刻化しやすい点が特徴です。
- 農作物被害
農家にとっては害虫を食べてくれる益鳥でしたが、近年は農業の衰退と共にエサが減少し、農作物である果物や野菜への食害が問題になっています。大群で果樹園などに飛来し、農作物への被害が経済的損失につながっています。

- 都市部でのねぐら形成が社会問題に
特に都市部では、ムクドリの大群による騒音や糞害が社会問題となっています。例えば、東京都内の駅前では数千羽のムクドリが集まり、歩道が糞で覆われ清掃が追いつかない状況となり、行政による対策が講じられています。

- 鳴き声による騒音被害
鳴き声は「キュルキュル」「リャーリャー」「ギャーギャー」と大きく、群れで鳴くため、非常に騒がしく感じられます。特に夕方の帰宅ラッシュ時に駅前や街路樹に集まるため、駅前での騒音被害が深刻化する傾向にあります。住宅地にねぐらがある場合、睡眠障害やストレスの原因となることがあります。

- 民家への営巣による糞害や騒音問題
ムクドリは家の戸袋など建物のちょっとしたすき間に巣を作ることがあり、鳴き声や糞による悪臭、ダニの発生などが問題になることもあります。糞は雑菌を多く含み、掃除の手間だけでなく、感染症やアレルギーなど健康被害の原因にもなります。

ムクドリに有効な対策
多くの自治体では、ムクドリの大規模なねぐらや集団被害が発生した場合、音や光による威嚇や追い払い、ねぐらとなる樹木の剪定などを実施していますが、被害の大きい地域での一時的な対策が中心で、根本的な解決には至っていません。都市部で生活することでの騒音や人の動きにもかなり慣れており、10mくらいに近づいても逃げないことが多く、危険が少ないと判断すれば大胆に行動することもあります。こうした知性と順応性が、都市での大規模な群れ形成を可能にし、防鳥対策を難くしている一因でもあります。

フジナガでは主に、防鳥ネットによる対策を実施しています。ムクドリはスズメより一回り大きく、ハトよりは小柄なので、ハトに対する目幅50mmのネットでは効果が得られません。ムクドリの対策にはスズメ同様に目幅15mm程度の防鳥ネットが効果的です。

当社のバードネットは、鳥の種類ごとに網目の幅が設計されているので、ムクドリなどの小さな鳥にも対応可能で、鳥が絡む事もなく安心です。極細で軽いネットなの圧迫感がなく、美観も損ねません。
フジナガでは長年培ってきた鳥害対策の知識や経験を活かし、ネットの目幅だけではなく、取付金具の間隔もムクドリに合わせたピッチにするなど、隙間を極力なくす施工を行っています。
高い適応力でたくましく生きるムクドリ。人との共生が課題
ムクドリは環境変化に柔軟に適応し、都市と自然のはざまでたくましく生きる賢い鳥です。農業の衰退や都市化が進んだことで私たちの生活圏に進出し、糞害や騒音被害などが問題視されるようになりましたが、ムクドリを過度に駆除すると、農地の害虫被害が増加するなど、生態系への影響も懸念されます。

「鳥と人との共生」を目指し、ムクドリの生態や習性を正しく理解した上で、適切な対策と配慮を行うことが、今後ますます重要になるでしょう。フジナガでは、これからもムクドリを傷つけることなく、「鳥と人との共生」を軸に、鳥害対策に取り組んでいきます。