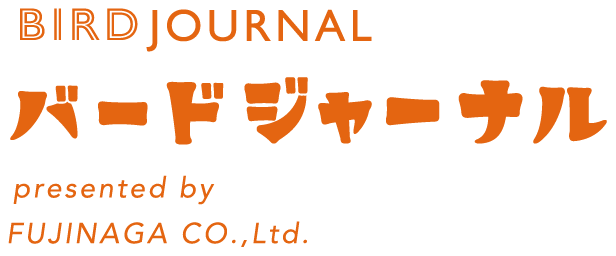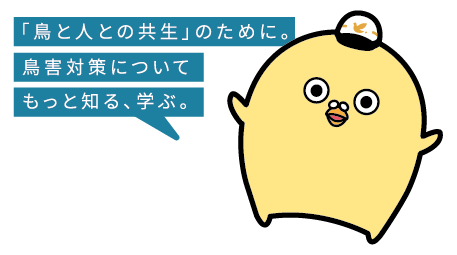私たちの住む街のあちこちで見かけるハト。とても身近な存在ですが、その生態については詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
フジナガは「鳥と人との共生」を目指し、鳥を傷つけることなく、鳥と人との生活エリアを分けられるような鳥害対策を行っています。そのためには鳥の習性や行動パターンを知ることは必要不可欠です。
今回は、押さえておきたいハトの生態や習性、行動パターンについて、鳥害対策の専門業者の視点で詳しく解説します。
ハトの種類と特徴
世界には約300種がいるとされているハトですが、日本で主に見られるハトは「ドバト(カワラバト)」と「キジバト」の2種類です。
ドバト(カワラバト)

全体が灰色で首元が光沢のある緑色をしたハトを公園などでよく見かけると思いますが、あれが「ドバト」です。
一般的に「ドバト」と呼ばれていますが、種類としての正式名称は「カワラバト」で、もとは中央アジアなどに分布していたものが1500年ほど前に日本に渡来した外来種です。
伝書鳩やペットとして人が飼育しやすいように品種改良されたカワラバトが、逃げて野生化したものを「ドバト」と呼ぶようになったと言われています。その由来は「塔に住むハト(塔鳩)」や「寺のお堂に住むハト(堂鳩)」からきているという説もあります。
【特徴】
・ 全長約30~35cm
・ 鳴き声は「クルックー」
・ 群れを作って行動する
・ 人に対する警戒心があまりない
【羽色】
全体が灰色で翼に2本の黒い線が入ったものや、黒と灰色のまだら模様、全体が赤茶色など、個体によってさまざまです。
【生息地・営巣の場所】
農村地域や市街地に生息し、公園や駅前など人の多い場所に集まります。
野生のカワラバトは本来、断崖絶壁の崖や岩場で巣作りを行っていたので、その習性から市街地に住むドバトはマンションのベランダや高架下など高所で外敵に狙われにくい場所に巣を作ります。
キジバト

「キジバト」は、「ヤマバト(山鳩)」とも呼ばれ、主に山岳地帯に生息していた種類ですが、森林の開発などにより環境が変化したことから農村地域にも住み着くようになり、近年では市街地で見られることも増えています。
キジの雌に体色が似ていることが名前の由来とされています。
【特徴】
・ 全長約33cm
・ 鳴き声は「デーデー、ポッポー」
・ 1羽またはオスとメスの2羽で行動する
・ 人に対する警戒心が強い
【羽色】
赤茶色の羽根でキジに似たウロコ模様、首に青い縞模様があるのが特徴です。
【生息地・営巣の場所】
多くが山地、農村地域に生息し、木の上に巣を作ります。
市街地では公園の木や街路樹の上に巣を作ることもあります。
ハトの食性
ここからは、主に市街地に生息し、個人宅での被害が多いドバトの生態を中心に紹介します。
ハトは基本的に雑食性で、主に植物の種や穀類、豆類を食べる草食性傾向があります。
人に近い場所に生息するようになったことから、人間が与えるエサや地面に落ちているお菓子のくずを食べるなど、食性も変化しているといえます。ただし、カラスほど雑食ではなく、生ゴミを漁ることはありません。

また、通常鳥が水を飲むときは、上を向いて流し込みますが、ハトは鳥にしては珍しく、水にクチバシを差してそのまま吸い上げて飲むことができます。

ハトの天敵
ハトにとっての天敵はカラス、タカ、ワシ、フクロウ、ネコ、ヘビ、イタチなどです。これだけ天敵がいれば、ハトの数が急激に増えることもないように思えますが、「市街地」という環境下では事情が変わってきます。
猛禽類のタカ、ワシ、フクロウは肉食なのでハトを襲って食べることもありますが、市街地にはほぼ生息していないので襲われることはそうありません。
雑食であるカラスはハトを襲うこともありますが、街中には他にエサが豊富なので、積極的にハトを狩ることもありません。ネコも同様です。
マンションのベランダなど高い場所に巣を作れば、ネコやヘビ、イタチといった地上の敵に襲われることも少なくなります。
つまり、市街地に住むハトは実質天敵がいない環境で暮らしているといえるのです。

ハトの繁殖
ハトは一夫一妻で1度に2個の卵を産み、孵化までは約18日間、ヒナは1ヶ月程度で巣立ちます。ヒナを育てている最中に次の産卵をすることもあり、年間5、6回の繁殖が可能です。

スズメなど他の野鳥は親鳥が虫などのエサを調達してヒナに与える必要があり、エサの多い春から夏頃が繁殖期となりますが、ハトはオスもメスも体内で「ピジョンミルク」と呼ばれるタンパク質や脂肪が多く含まれた物質を作り出す能力を持っているため、エサの少ない冬でも子育てができ、一年中繁殖が可能なのです。
巣立ち後、半年で繁殖が可能で、メスで10歳、オスで12~13歳くらいまで繁殖能力があります。ちなみに野生のハトの寿命は平均10年程度と言われていますが、ペットとして飼われているハトは20年以上生きる個体もいるそうです。
この繁殖能力の高さが、ハトの個体数増加の一因となっています。
ハトの生活リズム

ハトの行動範囲は約20kmと言われています。数羽から数十羽の群れで過ごしますが、多いときは100羽以上の群れを作ることもあります。昼行性で、以下のような生活リズムで行動しています。
- 朝・・・太陽が昇ると行動を開始し、巣の近くの公園などエサ場に出向いてエサを探す
- 昼・・・エサ場を観察しやすい見晴らしのいい場所で休憩。日向ぼっこや水浴びをして過ごす
- 夜・・・自分の巣や、建物の軒下や橋桁などに集団でねぐらを作って眠る
ハトの習性・行動パターン
ハト対策のカギとなる、ハト特有の習性や行動パターンについて具体的に紹介します。

- 帰巣本能が高い
ハトは強い帰巣本能を持っており、500~1000㎞離れた場所からでも巣のある場所に戻ってくることができると言われています。伝書鳩や鳩レースはこの帰巣本能を利用しています。

- 人に対する警戒心がない
元々人が飼いやすいように品種改良されたドバトなので、人への警戒心はかなり低く、人の近くにいると天敵が近寄らないということもあり、人の生活圏の近くに巣を作る傾向にあります。
とはいえ、人が常に出入りしたり巣に触られたりするのは避けたいようで、見えにくい室外機の下や空き家など、人と「近からず遠からず」の距離感がある場所を好みます。

- 縄張り意識、巣への執着心が強い
ハトは縄張り意識が強く、自分の縄張りや巣に危害を加えようとする存在に対しては闘争して追い払うほどです。
また、ハトは巣を作る前にその場所が安全であるか念入りに確認した上で営巣します。そのため一度巣を作ったらその場所への執着心は強く、たとえ追い払われても簡単には諦めず、何度も同じ場所に巣を作ろうとします。

- 巣を作る前の行動パターンが存在する
ハトが巣を作るまでには、決まった行動パターンが存在します。
01.「あの場所がよさそうだ」という場所を見つけたら、その場所がよく見える高所にとまって様子をうかがいます。例えばあるマンションのベランダに狙いを定めたら、反対側の建物の屋上や電線などから、天敵が寄ってこないかなど慎重に様子をうかがいます。
02.安全を確認するため、警戒しながらその場所に降り立ちます。ベランダなどであれば、まず一番端の手すりで羽休めしながら、この場所が安全か、居心地がいいか、巣を作れそうか、ベランダ内部の様子をうかがいます。
03.安全が確認でき「巣を作る場所としてよさそう!」と認識したら、早速巣を作りはじめます。
ハトの習性をふまえた対策のコツ
ハトは繁殖能力も高く、市街地で数が増えていることから、糞害などの被害が拡大しています。また、ハトの帰巣本能は他の動物と比べ強いため、一度巣を作ってしまうとどんなに追い払われても何としても巣に帰ろうとします。こうなってしまうと対策が難しいので、最初からハトを近づけないようにするのが一番の解決策といえるでしょう。ハトの習性を踏まえた対策のコツをいくつか紹介します。
「安全ではない場所」と認識させる
ハトは人に対する警戒心が低いとはいえ、人の気配が常にある場所、人の目に留まりやすい場所は避ける傾向にあります。ハトの糞をこまめに掃除し常に綺麗な状態を維持すること、物を放置せずに巣が作りやすい環境を作らないことで、「人がよく立ち入る安全ではない場所」とハトに思わせることが大切です。
⇒ ハトの糞の掃除についてはこちらでも詳しく紹介しています

様子見する場所への着地を物理的に防止する
ハトは巣を作る前の様子見のために、ベランダの一番外側にある手すりにとまる習性があるので、バードピンやバードワイヤーを設置し、物理的に止まらないようにさせるのがベストです。

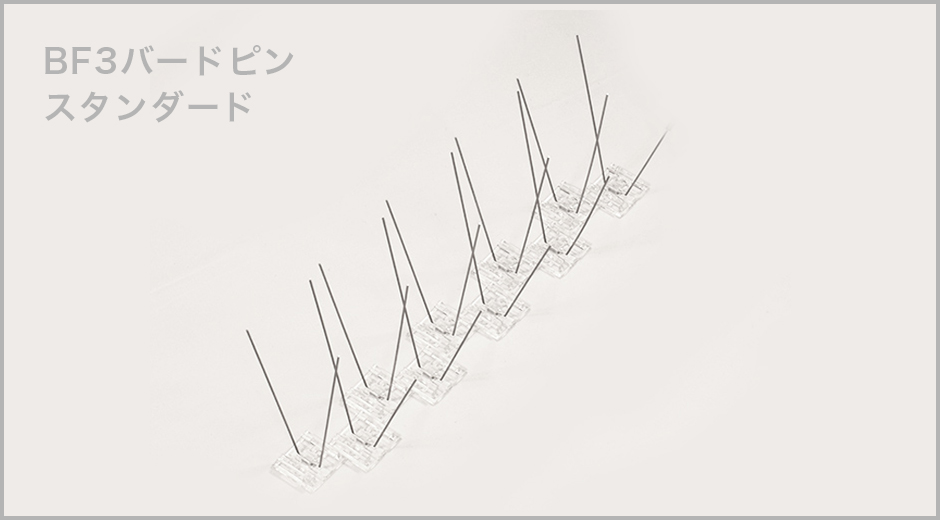

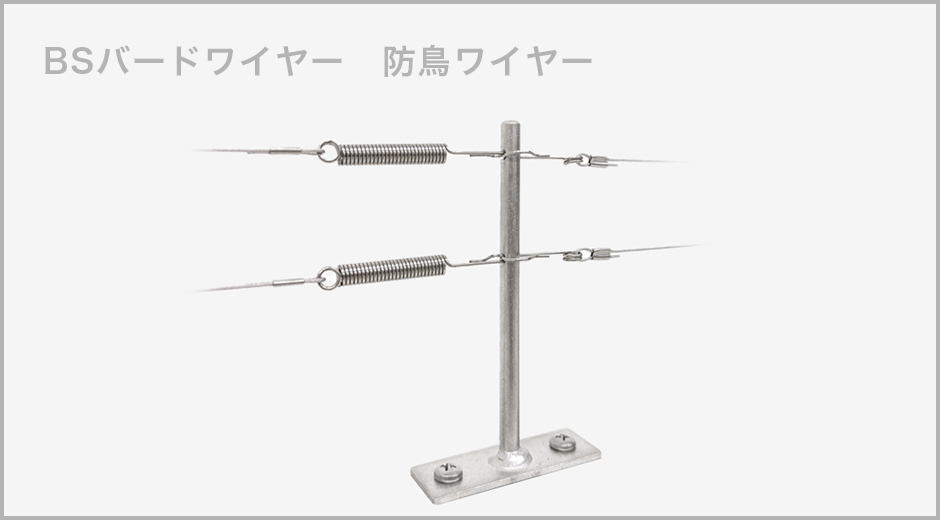
巣への執着心が強い場合はバードネットの隙間に注意
すでにハトが巣を作り執着心がかなり強くなっている場合は、侵入を防ぐために個人でバードネットを貼っても、わずかな隙間から入りこみ再び巣を作る可能性が高くなります。高所でのバードネットの設置は危険も伴いますので、プロに依頼することをおすすめします。

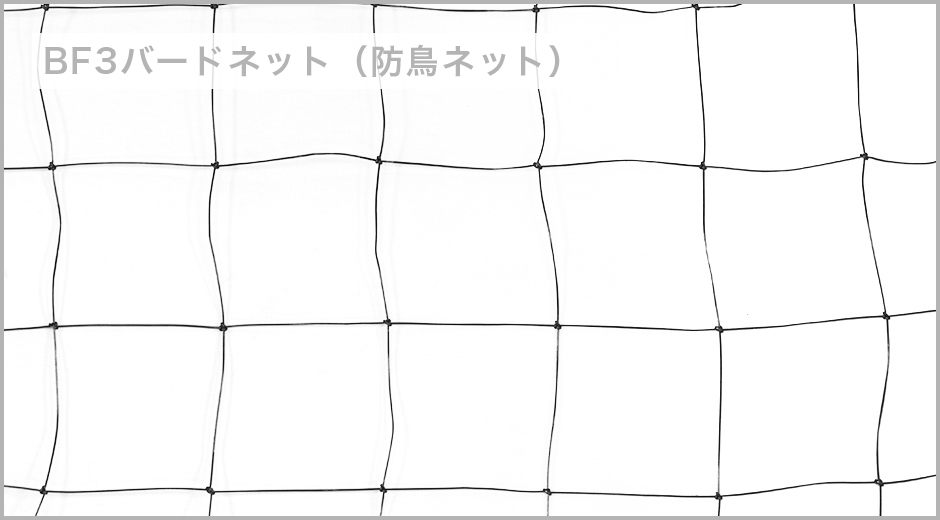
BF3バードネットは5年間の効果保証がついているのもポイントです。実施後に鳥の侵入、停滞などが確認された場合は無料で改善処置を行っています。
ハト対策はハトの生態を熟知したプロに任せるのがおすすめ

ハト対策は、相手が生き物であるだけに難しく、弊社のような専門業者でも、ハトの生態や被害状況、周囲の環境などさまざまな要素を視野に入れ、慎重にプランを練った上で対策を講じています。フジナガは、「鳥と人との共生」を社是とし、鳥を傷つけない鳥害対策アイテムの開発や、鳥の生態保全を前提とした鳥害対策の推進に取り組んでいます。長年の経験と、累計7万件(※)の施工実績で培った技術で「鳥と人との共生」をお助けしますので、鳥害にお困りの際はぜひご相談下さい。
※2021年5月時点