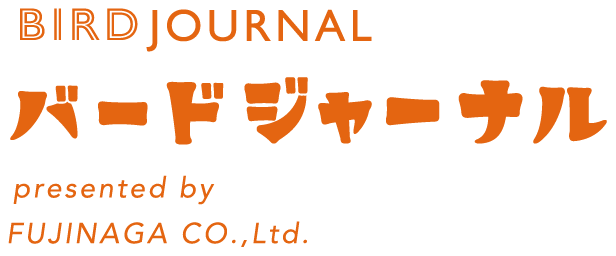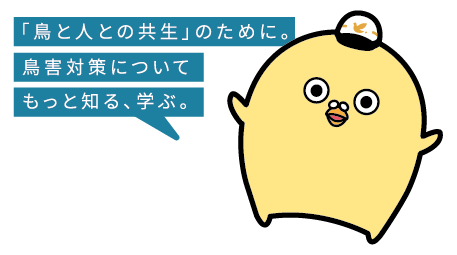ほっぺに黒い斑点、つぶらな瞳、ふっくらとした愛らしいフォルム。屋根の上や電線で「チュンチュン」とさえずるスズメは、私たちの日常に自然と溶け込んでいます。「枕草子」や昔話、童謡にもたびたび登場し、古くから親しまれてきたスズメは、日本人にとって最も身近な野鳥といえます。しかし、そんなスズメの生態については、意外と知られていません。
今回は、スズメの生態や被害、対策について詳しく解説します。スズメへの理解を深めることで、共生のヒントが見つかるかもしれません!
スズメってどんな生き物?
01. スズメの種類と特徴
スズメは日本人にとって最も身近な野鳥であり、「スズメ目スズメ科スズメ属」に分類されます。世界には20種類以上ものスズメ属の鳥がいると言われていますが、日本で見られる主な種類は「スズメ」と「ニュウナイスズメ」の2種類です。

「スズメ」は普段、街中や公園で見かける機会が多いですが、「ニュウナイスズメ」はその姿を見かける機会が少なく、名前を初めて聞いた方も多いかもしれません。
ニュウナイスズメの最大の特徴は、スズメのトレードマークともいえる頬の黒い斑点がないことです。繁殖期以外はニュウナイスズメ単独種で群れをつくりますが、少数の場合はスズメの群に混じることもあります。スズメの群れを見つけたら、頬の黒斑がないニュウナイスズメがいないか、探してみてください。

【スズメとニュウナイスズメの主な違い】
- スズメは頬に黒斑がある
ニュウナイスズメは頬に黒斑がない

- スズメの頭部は茶褐色。オス、メスともに同じ体色
ニュウナイスズメのオスの頭部は明るい栗色。メスの頭部は薄茶色で太い黄土色の眉斑がある


- スズメは日本全国の街や農耕地など、人の生活圏に近いところで生息している
ニュウナイスズメは山地や林など自然に近い環境で生息している

- スズメは季節による移動をせず一定の地域で暮らす留鳥(りゅうちょう)
ニュウナイスズメは北海道や本州中部以北の山地で繁殖し、冬は暖地へ移動する漂鳥(ひょうちょう)

02. スズメの生態
ここからは、私たちの身近にいる「スズメ」の生態について紹介します。
- 日本全国で見られる身近な野鳥
体長約14~15cm、重さ約25g。日本では小笠原諸島を除く全国に分布し、人家や農地、公園など身近な場所で暮らしています。

- 頬の黒斑がトレードマーク
頭から背中が茶褐色で、頬と喉に黒斑があるのが特長です。茶褐色の羽には黒と白の模様があります。オスとメスで同じ体色をしており、見た目では区別がつきません。

- 人の近くで暮らすが、警戒心は強い
民家の屋根瓦の下や換気口、建物の隙間、看板裏など人工物の隙間に巣を作ります。巣材には枯草や羽毛のほか、ビニール片など人工物を利用することもあります。
人の近くで子育てをすることで、ワシなどの猛禽類、ネコ、イタチ、カラスなどの天敵から身を守っていると考えられますが、人への警戒心も強く、なかなか人には慣れません。周囲に敏感に反応し、危険を察知するとすぐに飛び立ちます。

- 季節で変わる食性
雑食性で、秋~冬は主にイネ科などの乾いた種子を好み、春~夏の繁殖期にはヒナを育てるために昆虫類(幼虫)を多く採食します。市街地ではパンくずなど、人間の食べ残しも食べることがあります。
米農家にとってはイネに付く害虫を食べてくれる益鳥であり、一方で、夏から秋にはそのイネを食べる害鳥としての一面も持ち合わせています。

- 益鳥・害鳥の両面性
米農家にとってはイネに付く害虫を食べてくれる益鳥であり、一方で、夏から秋にはそのイネを食べる害鳥としての一面も持ち合わせています。

- つがいで協力して子育て
繁殖期は3月~8月で、年に1~3回繁殖します。オスとメス共同で抱卵し、雛は約15日で巣立ちます。

- 両足をそろえて跳ねるホッピング
地上では両足を揃えてピョンピョン飛び跳ねるように移動します。これは「ホッピング」と呼ばれ、樹上で生活する小型の鳥に見られる歩き方です。

- 水浴びと砂浴びの両方を行う珍しい鳥
鳥は体についた寄生虫などを落とし、羽毛を清潔に保つために、「水浴び」か「砂浴び」のどちらかを行う習性があります。スズメは鳥の中でも珍しく、水浴びと砂浴びの両方を行います。

03. スズメと人の関わり
スズメは、単なる身近な鳥以上に、昔話や生活文化の中で長く愛され、日本人の感性や日常に溶け込んだ存在と言えます
- 家紋としてのスズメ
「雀紋(すずめもん)」として日本の家紋にも使われています。代表的なものに「ふくら雀」「三羽雀」「雀の丸」などがあり、特に「竹に雀」は、戦国武将の上杉謙信や伊達家が使用した家紋として有名です。
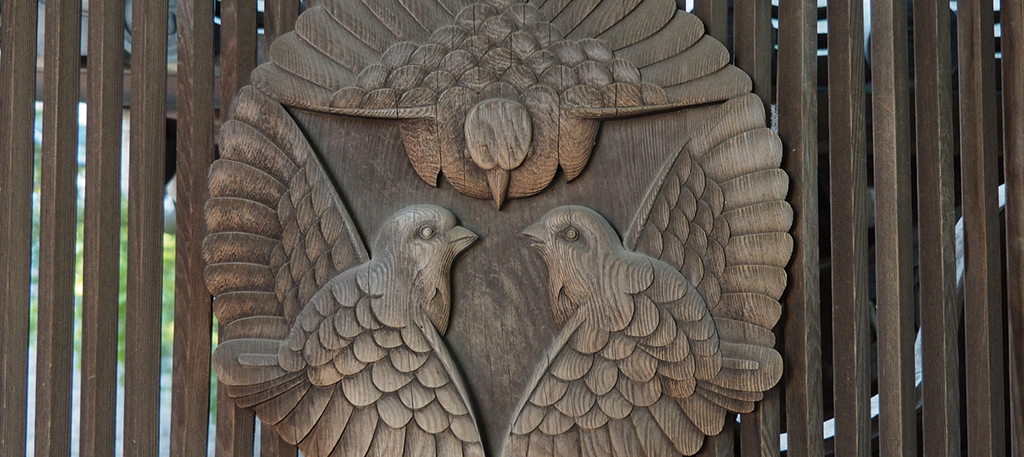
- 昔話や文学の題材にも
昔話「舌切り雀」や落語「抜け雀」など物語にもよく登場し、俳句や短歌では「寒雀」「ふくら雀」「稲雀」など、季語としても多く使われています。親しみやすい小鳥として日本人の心に根付いているといえるでしょう。

- 縁起の良い「ふくらすずめ」のデザイン
冬の寒さから身を守るために羽を膨らませて丸くなったスズメの姿をモチーフにした「ふくらすずめ」は日本の伝統的なデザインです。「福良雀」「福来雀」とも書かれ、「福を呼ぶ」「豊かさ」「子孫繁栄」の象徴とされ、古くから絵画や着物、器、ふすまなどさまざまな工芸品や日用品の文様として親しまれてきました。

スズメによる被害とは?
一見かわいらしいスズメも、時に人間の生活に影響を及ぼすことがあります。
- 農作物被害
スズメはイネやムギなどの穀類の種や苗を好んで食べます。特に収穫前のイネやムギが狙われやすく、巣立ち直後の若いスズメが大群で集まることで被害が拡大します。野菜の種や苗も食べられることがあり、被害は一年中発生します。

- 鳴き声による騒音被害
スズメの「チュンチュン」という鳴き声は、単体だと朝の訪れを告げる爽やかな声に感じられますが、これが大群で一斉に鳴くと騒音となり、睡眠障害やストレスの原因となることがあります。

- 巣作りによる糞害や建物の損傷
家屋や建物に巣を作られると、糞による衛生被害が発生します。掃除の手間だけでなく、感染症やアレルギーなど健康被害の原因にもなります。また、糞や巣材のワラが雨どいの詰まりや水漏れ、建物の損傷を招くこともあります。
スズメに有効な対策
スズメはわずかな隙間からでも侵入できるので、プロでも苦戦するほど難しく、高いレベルの対策が求められます。鳩やカラスと同じ対策を行うと、効果が全く得られないので、注意が必要です。
ハトに対しては網目の幅が50mm程度のネットが適していますが、スズメには効果がありません。スズメの対策には、目幅15mm程度のネットの設置が効果的です。

当社のバードネットは、鳥の種類ごとに網目の幅が設計されているので、スズメなどの小さな鳥にも対応可能で、鳥が絡む事もなく安心です。極細で軽いネットなの圧迫感もなく、美観も損ねません。
ただし、目幅が小さいネットで塞げばスズメが侵入することはないのか・・・というと、残念ながらそういうわけにもいきません。ネットの目幅だけではなく、取付金具の間隔もスズメに合わせたピッチにしなければいけません。フジナガでは長年培ってきた鳥害対策の知識で、スズメのような小さな鳥が侵入しないよう、限りなく隙間を生まない施行を行っています。
スズメの数が減っている!?人とスズメの共生が課題
「最近、スズメを見かけなくなった」と感じている方も少なくないのではないでしょうか?
実際に、環境省と日本自然保護協会の調査によると、スズメの個体数は年3.6%のペースで減少しており、これは絶滅危惧種の基準に相当する数字です。このままのペースで減少が続けば、スズメが絶滅危惧種に指定される可能性も指摘されています。住宅事情の変化による営巣場所の減少や、水田・草原の減少によるエサ不足、環境の変化などが主な原因として考えられています。
スズメは米農家にとってイネを食べる害鳥でもある一方、害虫を食べてくれる益鳥でもあります。スズメの鳥害対策では、生態系のバランスを保ちつつ、人間との適切な距離感を維持するため、生態や習性を理解した上で、適切な対策をすることが求められます。
フジナガでは、これからもスズメを傷つけることなく、「鳥と人との共生」を軸に、鳥害対策に取り組んでいきます。