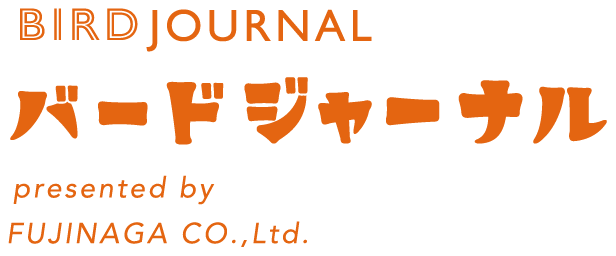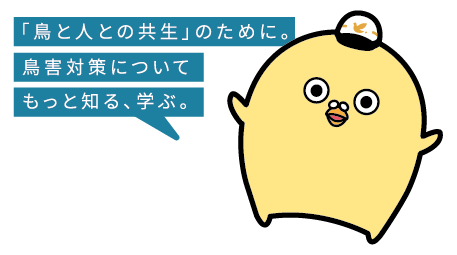全国各地で活躍するフジナガ社員たちが、日々の経験から得た知見や業界トレンドを臨場感たっぷりにお伝えする新企画「現場発!鳥害対策のリアルストーリー」。
第五回となる今回は、九州支社で営業課長代理を務める松永貴博さんにインタビュー。
豊富な対策実績を持つ松永さんに、鳩の侵入リスクの高い場所や、現地調査の際に気をつけていること、印象深い事例について伺いました。鳩がどのようにして人の目をかいくぐり、施設に深刻な被害をもたらすのか——現場の舞台裏と対策の最前線に迫ります。

九州支社 営業課長代理 松永貴博さん ( 2016年入社 )
現場で培った経験値
鳥害対策では、まず鳥の侵入経路を突き止めることが重要だそうですね。
はい。鳥がすでに巣を作っている場合は、まず侵入経路を特定し、ネットなどでそれを封鎖することが第一歩です。
侵入経路は、鳥の大きさや、建物の構造によって様々です。例えば鳩でいうと、マンションの場合はバルコニーや廊下の開口部から直接入ってくるケースがほとんどなので単純です。しかし、倉庫や立体駐車場、工場のような大規模施設は構造が複雑で、プロでも発見に苦労することがあります。
鉄骨構造の建物の侵入経路として代表的なのは、鉄骨と建物の接合部や、H鋼が庇につながる部分など、外部と内部がつながる部分に隙間ができやすく、そこから鳩が出入りするケースが多いですね。
▼ マンションや倉庫の鳥害についてはこちらでも詳しく解説しています。

現地調査ではどのような点に注意されていますか?
過去の経験や、鳩の習性をもとに「鳩ならここを好むだろう」と感じる箇所や、構造的にリスクが高い箇所を重点的に確認します。説明が難しいですが、現場に入った瞬間に“違和感”を感じることもあります。それは“経験に裏打ちされた直感”といえるかもしれません。
また、固定観念を持たないことも大切です。「新しい建物だから隙間はないはず」と思っていたら、実際には塞がれていなかったケースもありました。
肉眼で確認できない隙間に携帯を差し込んで撮影したり、手を伸ばして触ってみたりと、地道な調査を重ねています。お客様が「どこから入っているのか見当もつかない」とおっしゃる場合も、必ず侵入口は存在します。大事なのは“鳩の目線”で建物を見ることで、鳩が好む安全な空間が見えてくるんです。
▼鳩の習性についてはこちらでも詳しく解説しています。
被害を未然に防ぐ使命感
鳩は小さな隙間からでも侵入できると聞きます。
そうなんです。7㎝四方の隙間があれば十分です。「こんな狭いところに入れるわけがない」と思うような場所でも、器用に入り込んでしまうのです。
「これくらいの小さな隙間なら大丈夫だろう」と思って放置すると、思わぬ被害が生じてしまうこともあります。私が対応した現場では、波型の折板屋根の三角金物が1箇所外れていただけで、そこから鳩が侵入し天井裏に巣を作っていました。このように“常識では考えられない場所”から侵入してしまうのが、鳩の厄介なところです。
外部から見えない場所に巣を作られると、被害発覚までに時間もかかります。ある倉庫では、鉄骨の接合部にできた微細な隙間から鳩が侵入し、屋根裏に営巣。やがて大量の糞が堆積して天井にシミができたことで、ようやく発覚しました。
鳥害を放置すると、どんなリスクがあるのでしょう?
最も深刻なのは糞害です。鳩の糞は酸性なので、金属やケーブルを劣化させる原因となります。特にエレベーターや機械設備では、重大な故障や全面交換につながりかねません。また、糞に含まれる病原菌が空気中に拡散すれば、施設利用者の健康被害につながる危険もあります。食品工場や医療施設においては、衛生管理上の大問題となります。
さらに、鳩には強い帰巣本能があり、一度安全だと認識した場所に執着し続けます。繁殖力も高く、短期間で数十羽に増えてしまうこともあり、被害はあっという間に拡大します。
▼健康被害についてはこちらでも詳しく解説しています。
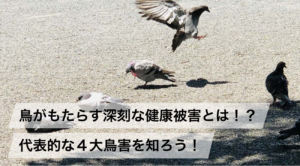
⇒ 鳥がもたらす深刻な健康被害とは!?代表的な4大鳥害を知ろう!

印象に残る現場エピソード
特に印象に残っている現場はありますか?
ある機械式の立体駐車場での事例です。内部に鳩が巣を作っていて、糞害が深刻化していました。エレベーター会社からも「放置すればケーブルが劣化し、エレベーター設備の全面交換が必要になる」と警告されたとのことでした。
外部から建物に入るには1階の出入り口しかなく、車が入る時しか開きません。そのタイミングを見計らって鳩が歩いて侵入するとは考えにくいため、別の侵入経路を疑いました。調査の結果、屋上の渡り廊下の鉄骨下に7㎝四方の隙間があることを発見しました。鳩はそこから侵入し、巣を作っていたのです。

そういったケースでの対策として有効な施工方法は何になりますか?
ネットによる侵入口の封鎖が一番確実です。応急的に清掃や忌避剤で対応することもありますが、それは一時しのぎに過ぎません。侵入経路を完全に塞ぐことが根本解決策です。
ただし施工には工夫が必要です。建物の構造を熟知し、鳩の習性を踏まえた設計が求められます。たとえば、鉄骨の接合部や屋根裏の通気口など、見落とされがちな箇所にも細心の注意を払う必要があります。また、ネットを張る際には、隙間が残らないように施工精度を高めることが重要です。ほんのわずかな隙間でも鳩は入り込んでしまうので、完璧な封鎖が求められます。
さらに工場や倉庫では高所作業が多く、足場を組んでの作業になるケースもあります。費用面の制約もあるため、お客様と相談し、最適なプランを提案しています。
だからこそ、被害が深刻化する前の段階で侵入を察知し、早期に対策を講じることが重要です。それを使命として、私たち鳥害対策会社は日々業務に取り組んでいます。
▼防鳥ネットによる対策方法についてはこちらでも詳しく解説しています。
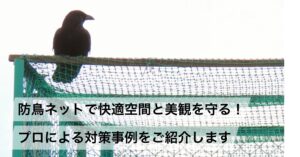
⇒ 防鳥ネットで快適空間と美観を守る!プロによる対策事例をご紹介します

これからの鳥害対策に向けて
鳩はなぜそこまでして隙間を探し、住み着くのでしょう?
鳩は非常に賢い生き物で、外敵に狙われず安全で、雨風をしのげる場所を本能的に選びます。我々の支店がある福岡も都市化や再開発が進み、自然も減っているため、従来の巣作り場所を失った鳩たちは新たな場所を求めて移動しています。つまり、人が環境を変えることで、鳩もまた新しい居場所を求めざるを得なくなっているのです。
だからこそ、鳩の習性を理解し、鳩より先に侵入経路を見破り、侵入される前に封じることが対策の核心です。
今後の鳥害対策の展望をどう見ていますか?
今後は、建物の新築・改修の段階から鳥害対策を組み込むことが主流になっていくと思います。実際、最近の新築物件では、通気口や鉄骨の接合部にあらかじめネットを張るなど、予防的な措置が取られるケースが増えています。これは、建築業界の意識も「鳥害は起きてから対応するものではなく、起きないように設計するもの」へと変わってきている証拠だと思います。設計段階から対策を講じることで、後々の対策コストや被害リスクを大幅に減らすことができますからね。
鳥害対策は、清掃や追い払いではなく、建物構造や鳥の習性を理解し、根本的な対策を講じることが不可欠です。特に鳩は執着心が強いので、対策は一度きりではなく、継続的な管理が求められます。
また、現場で得た知識やノウハウを、若手社員や協力会社の方々に共有していくことも重要だと感じています。現場でしか得られない“気づき”や“直感”があります。実際の現場に足を運び、鳩の動きや建物の構造を肌で感じることが、次世代の鳥害対策の質を高める鍵になると思います。
今後もこれまでの経験を活かし多くの現場で確実な対策を提供し、鳥害に悩むお客様の「困った」に、迅速かつ的確に応えられる存在でありたいと思っています。
興味深い話が聞けました。ありがとうございました。